
こんにちは。ミサゴパパです。
朝井リョウさんの小説『生殖記』を読み終えたとき、私はしばらくページを閉じることができませんでした。
胸の奥に重たい余韻が残り、人間とは何か、生きるとはどういうことか、そして「生殖」という営みは何のために存在するのか――そんな問いが、静かに、しかし確実に心の中で響き続けていました。
本作の主人公は、尚成という名の男性です。彼はゲイとして生きており、社会の中で自分らしく生きようとする一方で、「生殖することが前提とされる社会」に対して、どこか距離を置いています。
そしてこの物語の最も大きな特徴は、語り手が尚成本人ではなく、**彼の“生殖器”**であるという点です。
この驚くべき語りの仕組みは、一見奇抜に思えるかもしれません。しかし読み進めるうちに、そこには深い必然性があることに気づかされます。
語り手が「身体の一部」であるということは、つまり、意識や理性といった人間的な判断から離れた“肉体そのもの”の声が描かれるということです。
生殖器は、人間の中で最も「生物としての機能」を象徴する存在です。その生殖器が語り手になることで、私たちは自分の身体と心、そして社会との関係を、まったく新しい角度から見つめ直すことになります。
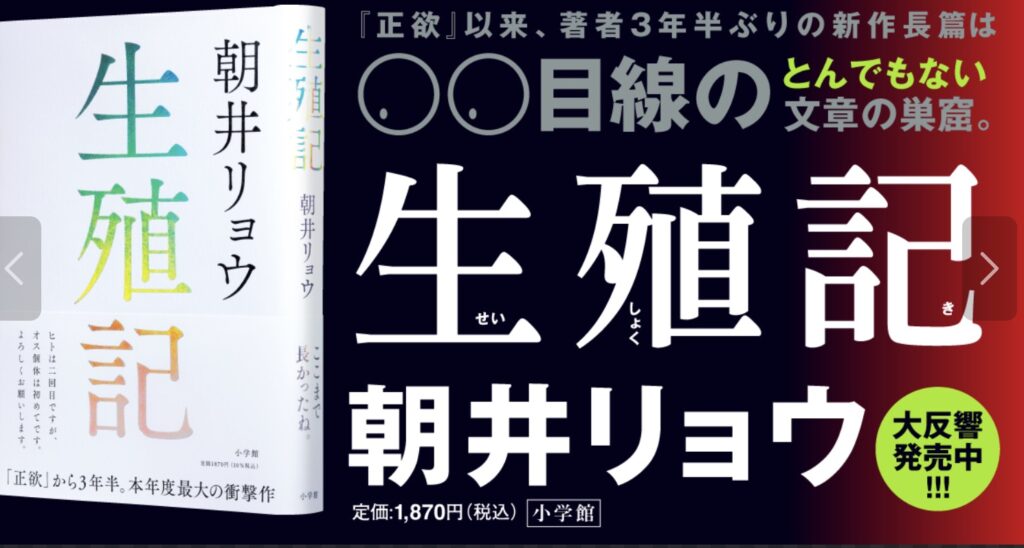
尚成は、自分が誰を愛し、どう生きるのかを自分で選び取ろうとしています。しかし、彼の身体――特に「生殖する機能を持ちながら、それを使わない身体」は、社会から見れば“異質”なものとして映ります。
この小説の中では、そうした社会的なまなざしが、静かに、しかし確実に描かれています。
「子を残すことが人間の使命だ」という価値観の中で、尚成という存在はどのように見られるのか。
そして、彼の生殖器自身は、その状況をどのように感じているのか。
語り手である「生殖器」は、時に淡々と、時に皮肉を込めながら、人間たちの生殖への執着や矛盾を見つめています。
それは決して露骨な表現ではなく、むしろとても静かで、客観的な語りです。
しかしその静けさの中には、強烈なメッセージが込められています。
「生殖」という言葉の背後にある社会的圧力。
「産む」「残す」「つなぐ」といった言葉に隠された、人間社会の期待や義務感。
そうしたものを、身体の視点から改めて問い直しているのです。
朝井リョウさんはこれまでも、『何者』や『正欲』といった作品で、社会が生み出す“正しさ”の形や、他者との違いに苦しむ人々を描いてきました。
『生殖記』は、その延長線上にありながら、さらに一歩深く、**「身体と社会の関係」**という根源的なテーマへと踏み込みます。
人間の身体は、生きるために存在するのか。
それとも、次の命を残すために存在するのか。
そして、もし生殖を行わない人がいたとして、それは「不完全な生」なのでしょうか。
こうした問いに対して、朝井さんは答えを示すことをしません。
むしろ読者に考える余白を与えながら、「生きること」そのものを静かに見つめ直すよう促しているように感じます。
その筆致は非常に繊細で、時に冷たくもありますが、同時にどこか優しさを感じさせます。
人間という存在の矛盾や限界を突きつけながらも、その内側に確かにある“尊厳”を見つめているのです。
読み終えたあと、私は自分の身体のことを考えました。
この身体は誰のためにあるのか。
社会のためなのか、家族のためなのか、それとも自分自身のためなのか。
『生殖記』は、そんな根源的な問いを私に投げかけてきました。
生きること、愛すること、そして生殖すること。
それらは似ているようでいて、実はまったく別のものかもしれません。
この作品を通して、私は「生」という営みの多様さ、そして人間の存在の複雑さに改めて気づかされました。
朝井リョウさんの『生殖記』は、決して軽く読める作品ではありません。
しかし、一度読み終えると、もう元の自分には戻れない――そんな強烈な読書体験を与えてくれる一冊だと思います。


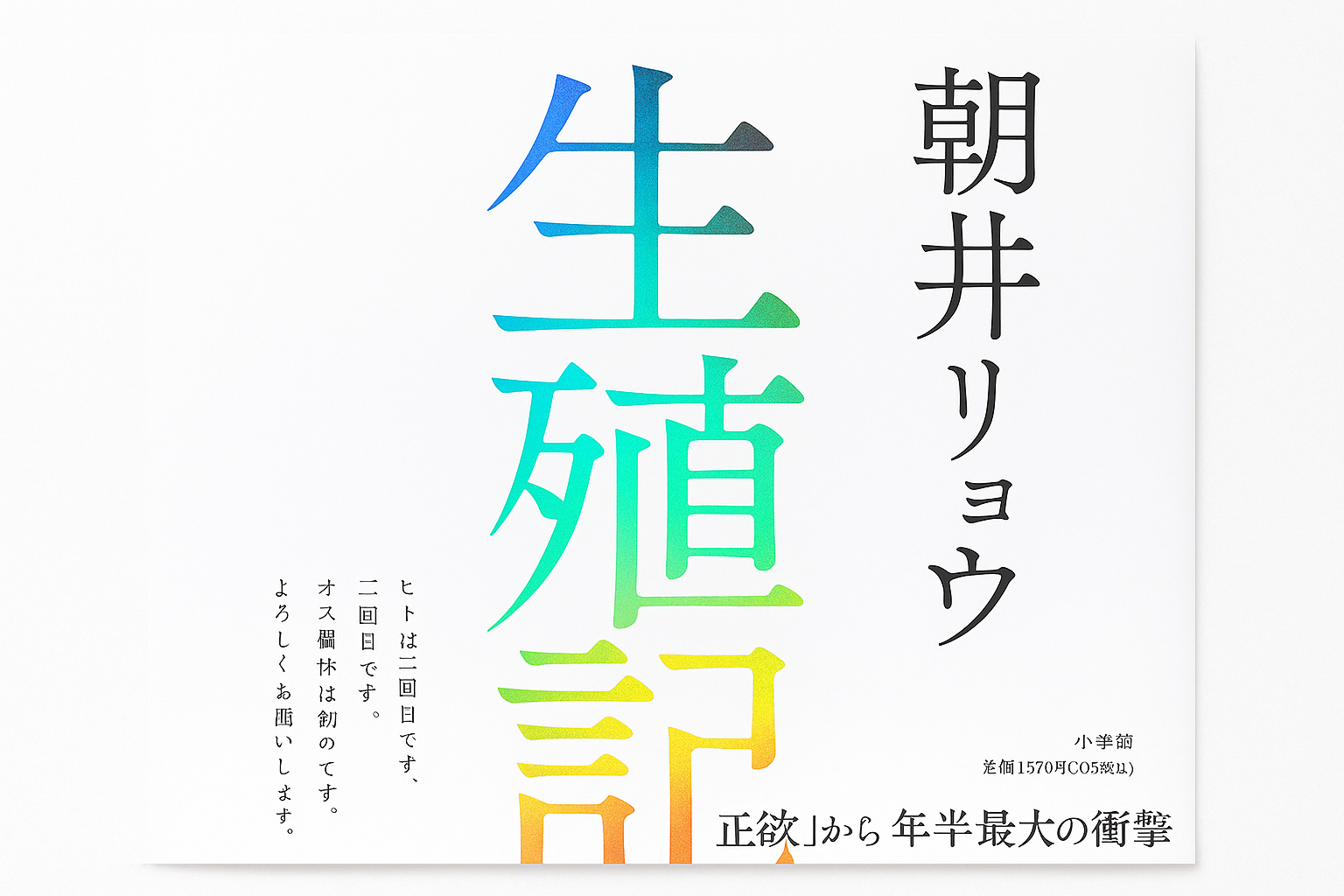


コメント